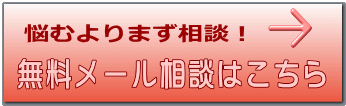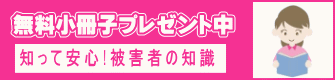脊髄損傷の立証のポイント。後遺障害について
TEL.03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
脊髄損傷の立証のポイント
1.脊髄損傷の有無が問題となるケース
脊髄損傷は、交通事故などの外傷によって脊椎損傷(骨傷=骨折や脱臼のこと)が起こり、それに伴って脊髄が損傷して発症します。
その場合は画像上の異常所見と神経学的所見・理学所見が整合すれば脊髄障害が比較的容易に認定されます。
それに対して、骨傷を伴わない脊髄不全損傷の場合には、脊髄障害の有無自体が問題となることがあります。
不全損傷のうち「中心性頚髄損傷」が特によく問題となりますが、これは中心性頚髄損傷の症状が、神経根を損傷した場合の症状とよく似ているためです。
→脊髄の不全麻痺、完全麻痺とは
また、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症(OPLL)、脊柱管狭窄症など、経年性の変形が認められる場合にも、経年性変化が交通事故とあいまって脊髄障害を発症したといえるのか、神経根症状(末梢神経障害)を発症したに過ぎないのか、そもそも事故後の症状と事故との因果関係があるか、なども問題となることがあります。
実際に「脊髄損傷」などの診断名があっても、自賠責保険や裁判で脊髄障害とは認定されないケースも少なくありません。
被害者としてはきちんと脊髄障害と認められるために、脊髄損傷という診断名のみに頼らず、脊髄損傷を裏付ける所見や症状経過などについて、きちんと立証していく必要があります。
2.脊髄障害(特に不全麻痺)の立証のポイント
不全麻痺とは脊髄横断面の一部が損傷された状態で、損傷部位以下の感覚・運動機能や深部反射に部分的な機能が残っていることを指します。
労災認定基準では「上肢または下肢を運動させることができても可動範囲等に問題がある」状態とされています。
不全麻痺は、脊髄半側損傷、中心性脊髄損傷、前部脊髄損傷、後部脊髄損傷など脊髄横断面の損傷部位によって症状が変わります。
→脊髄損傷の病態と評価
以下に立証のポイントを説明します。
画像所見
画像上で外傷性の変化が認められるのかを確認するのはもちろんですが、特にMRI検査で脊髄の形態変化(物理的に変形しているか)や髄内信号変化(脊髄のどこかの部分に明るく光る信号があるか)が認められるかどうかを精査する必要があります。
また、椎間板ヘルニアや後縦靭帯骨化症、骨棘等の、脊髄周辺にも変性所見があるのかどうか確認します。
MRI画像で髄内に高信号(白く光る)病変が認められることを理由の一つとして脊髄損傷(脊髄障害)があるとする例は多いのですが、裁判例では、T2強調画像で信号上昇がみられるものの、それが一般的にみられる中心性頚髄損傷に伴う経時的な変化とは一致しない、などとして脊髄損傷を否定したものもあります。
また、MRI画像で明らかな輝度変化等の異常所見が認められないことを理由に脊髄損傷を否定される例は多いのですが、一方でMRIで明らかな髄内輝度変化が認められなくても、脊柱管狭窄所見が認められる場合に、脊髄損傷と認められた裁判例もあります。
とはいえ、やはりMRIで輝度変化(脊髄の損傷部分が明るく光る)があることが、脊髄障害と認められるためには非常に重要になってきます。
神経学的所見の整合性
画像検査に異常が認められる場合は、その異常所見と神経学的検査所見が整合することを立証します。画像所見に異常があり、かつ例えば深部腱反射やホフマン反射テストで陽性の結果が得られれば、脊髄障害が認められる可能性が高いと言えます。
→神経学的検査とは
画像検査で、脊髄自体に明確な異常が認められないものの脊髄への圧迫が疑われるような変性所見が認められる場合には、神経根症(末梢神経障害)と判断されることが多くなります。
症状経過等
症状の経過や推移が脊髄損傷として合理的に説明できることや、交通事故の態様から脊髄障害の発症が不自然ではないことも、脊髄障害として後遺障害の認定を受けるためには重要です。
一般的に交通事故の神経症状は、事故直後が一番重篤であるはずですが、実際の事例では事故直後よりも後遺障害申請時の方が悪化しているケースも結構あります。
事故後の症状悪化が不自然で医学的に説明できなければ、交通事故の後遺障害としては否定される可能性が高いです。
判例では、事故後に脊髄圧迫が進行して症状が悪化したケースで、頚椎前方固定術を行った担当医の回答内容などから、同手術が行われるまでの症状悪化については事故との因果関係があると認めたものがあります。
ですが多くの場合、症状推移が外傷性の脊髄損傷と整合しない推移をたどっていると(以前よりも悪化しているなど)、事故との因果関係は否定されることになります。
その他
その他に、日常生活動作の能力程度、その生活状況等を説明、立証する必要があります。これは脊髄障害として麻痺の程度や範囲、そして介護の必要性などの認定を受けるために必要なこととなります。
これらは自分自身の言葉で説明するほかに、家族や身の回りの世話をする人たちから陳述書を書いてもらったり、その他にも診療録やリハビリの記録、介護・動作状況を記録した日誌等も参考にしていきます。
当然のことですが、日常生活動作・生活状況等の説明は、画像所見や神経学的所見と整合している必要があります。
| 関連項目 |
- 後遺障害の定義と系列
- 等級認定のルール
(併合、加重) -
診断書、レセプトのポイント診断書の見方
- レセプトの見方
- 後遺障害診断書のポイント
- 関節可動域について
-
部位別の障害等級認定基準部位別障害等級一覧表
- 眼の障害
- 耳の障害
- 鼻の障害
- ↳下肢の外傷・種類と
後遺障害 - もっと詳しく
当事務所について
- ハシモトのコラム
- 当事務所のサポート
- 過去の相談メール