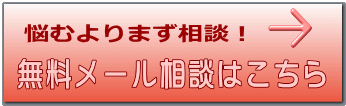脊髄損傷の病態と評価(中心性脊髄損傷)
TEL.03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
脊髄損傷の程度や状態を把握するためには
1.損傷高位(高さ)の評価
2.脊髄横断面での損傷程度の評価
この二つの側面から評価して病態を把握します。
1.損傷高位(高さ)による症状の特徴
脊髄が損傷された場合、大雑把に言うと、損傷部位から下にある部位の機能が障害(または消失)されます。
つまり首(頚髄)を損傷すれば、首から下の四肢の機能が障害(または消失)され、胸(胸髄)を損傷すれば胸から下の臓器・体幹・下肢等の機能が障害(または消失)されます。
腰(腰髄)を損傷すれば腰から下の、主に下肢の機能が障害(または消失)され、上肢に障害が出ることは無いとされています。
とはいえ、損傷高位の違いによる症状の特徴は実際にはとても複雑です。
頚髄損傷
頚髄損傷では、通常は四肢麻痺が認められます。この場合は四肢に感覚・運動機能の障害(または消失)をきたし、骨盤臓器に機能障害が現れます。
特に上位頚椎部(C1など上の方)の完全麻痺は致命的で、ほぼ不全麻痺のみが生存例となります。
この場合でも、四肢麻痺、四肢・体幹の感覚異常のほか、顔面にしびれなどの感覚障害を発症することがあります。
また中下位頚椎部(C2/3椎間からC7/T1椎間など)が損傷された場合には、その高位(位置)によって四肢の残存機能に差が出てきます。
胸髄以下の損傷
胸髄以下の部分が損傷された場合には、通常は対麻痺となり、両下肢及び骨盤臓器に感覚・運動機能障害が現れます。
上中位胸椎部(T1~T10/11椎間)の損傷は、完全麻痺となることが多いとされています。
腰椎部(L2/3椎間~仙椎、馬尾)の損傷の多くは不全麻痺で、両下肢、特に足関節の背屈が難しくなったり、母趾の伸展筋力が低下します。
2.脊髄横断面での損傷程度と特徴
脊髄横断面全体が損傷されれば、損傷部位以下が完全麻痺となります。完全麻痺の場合は脊髄損傷の診断はしやすいです。
それに対して脊髄横断面の一部分が損傷された場合、損傷以下の機能が不全麻痺となります。その部分が損傷されたかによって、麻痺の出方や残存機能が異なります。
完全麻痺
完全麻痺とは、脊髄が完全に損傷された状態で、脊髄横断面全体が損傷されており、損傷部位以下の機能が完全に麻痺していることを指します。
労災認定基準では「上肢または下肢が完全強直または完全に弛緩する」状態とされています。
不全麻痺
不全麻痺は脊髄横断面の一部が損傷された状態で、損傷部位以下の感覚・運動機能や深部反射に部分的な機能が残っていることを指します。
労災認定基準では「上肢または下肢を運動させることができても可動範囲等に問題がある」状態とされています。
不全麻痺は、脊髄半側損傷、中心性脊髄損傷、前部脊髄損傷、後部脊髄損傷など脊髄横断面の損傷部位によって症状が以下のように異なります。
| 損傷部位 | 損傷状態 | 症状 |
| 脊髄半側損傷 | 脊髄(横断面)の左右どちらか片側が損傷 | 損傷側:損傷高位で全感覚消失、同側下位に深部感覚・識別性触覚障害を生じる。損傷側の損傷部位以下で運動障害を生じる。 反対側:触角は保たれるが、温痛覚が障害される。 |
| 中心性脊髄損傷 | 脊髄中心部(灰白質)が損傷 | 多くの例で、下肢よりも上肢の麻痺が強く、痙性麻痺を呈し、手指の強いしびれと運動障害が残る。 触覚・深部感覚は保たれるが、温痛覚が障害される。 |
| 前部脊髄損傷 | 脊髄の前部が損傷 | 損傷部位以下で温痛覚障害、運動麻痺、膀胱直腸障害を生じる。感覚は触覚・振動覚・位置覚が保たれる。 |
| 後部脊髄損傷 | 脊髄の後部が損傷 | 同側の感覚(触覚、振動覚、位置覚)が障害されるため脊髄性運動失調を認めるが、運動機能は保たれる。 |
- 後遺障害の定義と系列
- 等級認定のルール
(併合、加重) -
診断書、レセプトのポイント診断書の見方
- レセプトの見方
- 後遺障害診断書のポイント
- 関節可動域について
-
部位別の障害等級認定基準部位別障害等級一覧表
- 眼の障害
- 耳の障害
- 鼻の障害
- ↳下肢の外傷・種類と
後遺障害 - もっと詳しく
当事務所について
- ハシモトのコラム
- 当事務所のサポート
- 過去の相談メール